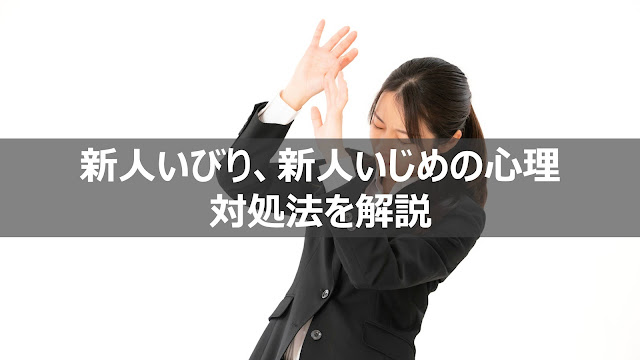会社や部署の規模、業界によりますが、たいていの職場では、ベテラン社員や、中堅、若手、新人といった広い幅の年齢層のメンバーが一緒に働いているかとおもいます。
どんな職場でも、組織の長期的な継続性を考慮すると、同じ年代、経験年数のメンバーでずっと仕事をしていくことは難しいですよね。
そのため一定の規模以上の組織では、定期的に経験の浅い「新人」を採用し、ベテランや中堅社員が時間をかけて教育して行くものであり、これはとても重要な事です。
ところが、この過程で、一部の組織では、新人の受け入れがスムーズに行かなかったり、ひどい場合は「新人いびり」とも思えるよな行為を行う先輩社員がいたりします。
その結果、せっかく採用した新人が育たない、新人が辞めてしまうといった問題が生じ、組織にとって長期的かつ大きな損失につながってしまいます。
こういった問題は、どこの職場、どこの業界でも起こりうることですが、そもそもこの「新人いびり」はどういった心理で行われているのでしょうか。
そこで本記事では、新人いびりのパターンや、新人いびりをする人は何を考えているのか(どういう心理なのか)?といった点について解説していきます。
加えて、新人いびりをする社員の取り扱い方についても整理していきます。
本記事は下記のような人向けになります、参考になれば幸いです。
・職場で新人いびりをしている人の心理が理解できない
・新人いびりをする人がいて、迷惑に感じている
・新しい職場で新人いびりにあっている、または新人いびりにあわないか不安
・組織内の「新人いびり」に対処する方法を知りたい
こちらの記事も
新人を辞めさせる人の心理と取扱説明書新入社員放置で「やることない」は大問題!原因と対策、やることリス
新入社員のミスはいつまで許される?ミスばかり・・・【隠すな、落ち込むな、見捨てるな】ありがちなミスと対策
新人いびりの心理とパターン。新人をいじめる人は何がしたいのかを理解する。
職場にせっかくはいった新人を受け入れられない、新人いびりをする人はどういった心理状態にあるのでしょうか、一体何がしたくて新人をいびったりいじめたりするのでしょうか。
新人いびりをする人を見て、
「ただの意地悪」
「新人にきつい、変わった人」
「新人ちゃん、いびりにあっても頑張れ」
といった軽い感じで考えてしまっている組織もあるかもしれませんね。
しかし、冒頭でもふれたように「新人いびり」は組織にとって、長期的な視点ではマイナスとなる要因ですし、放置することで、職場の雰囲気も悪くなりますし、将来の人材不足に対応できなくなるのです。
そのためにも、新人いびりの心理とパターンを理解して、きちんと対処しつつ、「新人いびりをする人」を正しく取り扱うことが重要になります。
新人いびりのパターン、典型例
ここでは、いわゆる「新人いびり」のパターン、典型例を紹介して挙げておきます。
・新人がミスをすると、必要以上に厳しく指導する傾向がある。
・新人の仕事のやり方や成果物に対し、あら捜しをして、些細なことにヒステリックに怒る。
・新人の仕事のダメ出しを上司に訴える。
・新人教育と称して、指導を積極的にするものの、指導が下手(毎回指示が違う、適切でない、やたらお説
教が長く簡潔に指導できていない
・逆に、新人を放置、冷遇というパターンも
こういった行動パターンを、新人が入るたびに示すようなベテラン、中堅社員(稀なケースで若手社員も)がいる組織では、何らかの対応が必要になってきます。
新人いびりの心理。新人をいじめる人がやりたいこと
新人いびりをする人の心理、新人いびり(新人いじめ)をする人がやりたいこと、背景には下記のようなものがあります。
・日頃のストレスのはけ口として、新人いびりをしている
・職場での自己の保身や、他者へのマウンティングや嫉妬から
・目の前の仕事への無駄に強い責任感
・歪んだ正義感とおせっかい
・無垢な新人への自身の価値観の押しつけ
「新人いびりの心理」というと、悪意があるものを想像しますが、中には良かれと思っていたり、自分として正しいことをしているつもりだったりもします(そのほうが厄介なケースもありますが)。
それぞれの詳細について、以下、解説していきますが、職場での「新人いびり」の実行者がどういう心理・意図でやっているのかは、対策を立てるにあたって非常に重要です。
新人いびりの心理:ストレスのはけ口
ベテラン社員や先輩社員による「新人いびり」「新人いじめ」と聞くと、「ストレスのはけ口といての新人いびり・新人いじめ」を真っ先に想像します。
こういったタイプの新人いびりでは、そもそも職場への不満があったり、自身の待遇に不満があり、自分よりも将来が明るい(ように見える)、かつ、立場の弱い相手(=新人)で憂さ晴らしをしているのです。
そのため、こういった心理が働いて、中堅以上の派遣社員が、正社員として採用された新卒への新人いびりを始める、といった事例も多いです。
この心理のもとに行われる「新人いびり」は、ぶっちゃけなんの生産性もないし、誰も幸せにならず、組織にとってマイナスでしかありません。
一方で、新人いびりをする本人だけが悪いというわけではなく、組織のあり方や、社員の扱い方に根本的な
問題が潜んでいる可能性もあるのです。
新人いびりの心理:自己の保身とマウンティング、嫉妬
組織に対する大きな不満はないものの、自分の保身と、新人に対する「マウンティング」のために、必要以上説教をしたり、厳しく接して、優越感に浸るめに「新人いびり」をする人もいます。
他人よりも心理的に優位に立ちたい、新人の立場を自分より低い位置に固定したい、というのはある種、人間という動物の本能なのかもしれません。
また、自分がマウンティングを取れる立場になるのを回避するための予防的な行動とも言えます。
はじめは指導と称して(必要以上に)厳しく接するものの、エスカレートしていくと、時間の経過とともに、放置、冷遇、必要な情報を与えないなどの、足を引っ張るような行為をするようになります。
これを放っておくと最終的には、組織が成果を出すことを妨害することに繋がりますので、はやめに対策を取る必要があるでしょう。
新人いびりの心理:無駄に強い責任感
新人に対して、悪意はないものの、新人教育や指導に(無駄に)強い責任感をもって取り組んでしまう人がいます。
その結果、周囲から「新人いびりをしている」とみなされるケースです。
この場合、本人は一生懸命、組織や新人の成長を考えているものの、必要以上に厳しく接したり、長々とお説教をするので、ぶっちゃけ迷惑です。
いくら責任感があっても、新人教育は正しくかつ効率よくやらないと逆効果ですし、新人も周囲もうんざりしているでしょう。
こういうタイプの人は、概して、あまり器用でなかったり、そんなに仕事ができるわけでもなく、実は自分の仕事でいっぱい、いっぱいになっていて、そもそも余裕がなかったりします。
新人いびりの心理:歪んだ正義感とおせっかい
職場で、やたら正義感を持って、他人の行動や考え方に口出ししてくる人っていますよね。
そこまでしなくても・・・と言いたくなるくらいやたら自分の正義感を押し付けてくるし、やりすぎだったり感覚が歪んでいたりするので、周囲は迷惑していたりします。
こういったタイプの人は、新人に対して、より一層に自分の正義感と正義の旗印を振って関わってきて、あれこれをお説教するといった「新人いびり」をやってしまいます。
本人は正しいことをしているつもりですが、歪んだ正義感から、業務上は無駄で生産性の悪い規則やルールを強要することも多々あって、迷惑なおせっかいとなってしまうのです。
新人いびりの心理:無垢な新人への自身の価値観の押しつけ
中途採用であれ、新卒であれ、新人というものは、はじめは当然、仕事のやり方や職場のルールを100%理解していないものです。
もともとそこにいる人たち絡みたらある意味「無垢」な状態。
こういった新人に対し、自身の価値観や仕事のやり方、「ここではこうあるべき」といった考え方を押し付けようとするタイプは「新人いびり」をしてしまいがちです。
「自分のやり方が正しいので、同じようにやってもわらないとこまる」
「今どきの新しい人はこんなこともしらない。自分が教えてあげる」
と考え、自分が教えたやり方でやっていないと不機嫌になったり、怒ったりします。
態度が気に食わないと、必要以上に強く接したり、逆に疎外したりしてしまうのもこのタイプ。
新人いびり、新人いじめをする人は女性が多い?男性は少ない?
一部の人は「新人いびり」「新人いじめ」をする人=女性が多いというイメージを持っているかもしれませんが、そうとも限りません。
女性か、男性かよりも、職場の状況や業種によるところが大きいし、上述のように、「新人いびり」「新人いじめ」をする人の心理によって、女性にありがちなパターン、男性にありがちなパターンというのもあります。
ただし、概して、女性のほうが職場で密な人間関係を築く傾向がありますので、女性から新人女性に対する「新人いびり」「新人いびり」がどうしても目立つ傾向はあるかもしれませんが。
新人いびり、新人をいじめる人が職場にあたえる悪影響
職場において、仕事を覚える前の新人への厳しい教育や指導は、ある程度は仕方がないことです。
経験のある誰かが近い距離で仕事のやり方や考え方を教えることで、新人は成長しますし、その結果、組織は持続的に成果を出し続けることができます。
とはいえ、いわゆる「新人いびり」「新人いじめ」といったものが横行する組織、あるいは、既存のスタッフが上述した「新人いびり」「新人いじめ」をやってしまう心理に陥ってしまう組織では下記のような問題、悪影響がでてきてしまいます。
・新人がいびりやいじめで辞めてしまい、慢性的な人手不足に陥る
・新人が育たない、育つのに時間がかかりすぎる
・「新人を育てる人」も育たない
・職場の雰囲気が悪くなる
・新人いびり、新人いじめをする人を、会社として信頼できない
時間とコストをかけて新人を採用するものの、結局育たないあるいは最悪辞めてしまうのです。
その結果人手が足りなくなり、また新人を採用します。
しかし、今度こそは新人を育てようとして「厳しく」接したところ空回り。
新しい人材は育たないのに、採用と育成コストばかりかかって、職場の雰囲気はどんどんわるくなる・・・という悪循環に陥ってしまいます。
新人いびりをする人、新人をいじめる人の取扱方法
そのため、組織としては「新人いびり」「新人いじめ」をやってしまう人(意図的であれ、良かれと思って空回りした場合であれ)を適切に取り扱う必要があります。
ここでは、新人いびりをする人、新人をいじめる人の取扱方法について考えて行きたいと思います。
「新人いびりをする人」、「新人をいじめる人」の取扱方法をざっくりと書くと下記のようなものがあります。
・「新人いびり」「新人いじめ」をする人を新人から遠ざける
・「新人いびり」「新人いじめ」をする人の職場で心理的安全性を確保する
・新人教育に関して無駄に大きなプレシャー、責任感を負わせない
・新人には「指導」や「お説教」ではなく「寄り添う」ことが重要
説明していきます。
「新人いびり」「新人いじめ」をする人を新人から遠ざける
当たり前かつ、即時の効果がある方法として、「新人いびり」や「新人いじめ」をやるような人は、新人から遠ざけるような配慮が効果的です。
この方法は「新人いびり」「新人いじめ」を意図的にやるタイプにも、意図せずにやるタイプにも有効となります。
まともに新人教育をできる人を教育担当者として公に指名して、それ以外の社員は基本的には自分の業務に集中してもらえるようにしましょう。
指名された教育担当者に、しっかりと教育をしてもらいつつ、「新人いじめ」「新人いびり」から新人を守ることもできます。
新人、教育担当者および上司の3者で成長度合いを確認しながら業務経験を積ませることができるので、管理者としても、最もやりやすい方法かと思います。
「新人いびり」「新人いじめ」をする人の職場で心理的安全性を確保する
上の方で書きましたが、「新人いびり」「新人いじめ」をやる人の一部には、
・日頃のストレスのはけ口として、新人いびりをしている
・職場での自己の保身や、他者へのマウンティングや嫉妬から
といった背景、心理状態にあることがあります。
これは言い換えると、「職場でなんらかの心理的な不安を抱えている」と言えます。
自分自身が無理なノルマやプレッシャーを抱えて追い込まれていたり、給与・待遇面で強い不満があるのかもしれません。
他人を貶めたり、他人に対してマウンティングを取らないと、自分が追い落とされるかもしれない、と不安になっているのです。
なので、こういったタイプに「新人いびりをやめなさい」と注意することもできますが、これでは根本解決になりません。
新人をいびったり、マウンティングを取らなくても、職場において、心理的に安全であること、居場所が確保できることを理解してもらうことが必要です。
具体的には、同僚、上司が下記のような働きかけをすることが効果的です。
・職場、チームで十分に役立っていることを言葉で伝える
・他人との比較ではなく、自分で自分を評価・褒められるようになることを目標にしてもらう
・日々の仕事っぷりに対して「ありがとう」と伝える
新人教育に関して無駄に大きなプレシャー、責任感を負わせない
新人教育という課題に、強すぎる責任感を感じてしまい、つい自分の仕事のやり方を押し付けたり、思うように新人が成長しないことを厳しく批判してしまった結果、意図せずに「新人いびり」「新人いじめ」をしてしまう人は意外と多いです。
組織が抱える(新人育成という)課題に、正面から向き合ってしまう「まじめ」で「不器用な」人に多い傾向で、決して悪いことではありません。
しかし、その結果新人が潰れてしまったり、職場の雰囲気が悪くなると本末転倒ですよね。
こういったタイプの人には、「過度な責任感」を抱えて、新人に接しないように、上司がしっかりサポートすることが重要です。
・新人の教育を一人で抱え込まなくても良いこと(組織全体で向き合うべき問題だということ)
・他者の育成は想像以上に難しく、そのことを上司や会社はちゃんと理解していること
・結果的に新人が思うように成長しなくても、それがすべて教育担当者の責任ではないこと(新人本人の能力や脂質によるものが大きいこと)
といったことを、しっかりと言葉で伝えると、教育担当者や先輩社員たちを、過度な責任感から開放させることができます。
新人には「指導」や「お説教」ではなく「寄り添う」ことが重要
新人の育成というと、仕事のやり方を一方的に「指導」することや、悪い部分・できてない部分を指摘して「お説教」によって是正していくイメージをもつ人がいます。
こういった人は、知らず知らずのうちに「新人いびり」や「新人いじめ」をしてしまいます。
ところが、実際は、新人といえど、いい大人なわけで、注意されたり怒られたりすることが、能力開発や成長につながることは稀です。
まともな社会人であれば、新人とはいえ、「職場で重要とされていることは何か?」、「業務上必要な知識やスキルはなにか」を理解しつつ、その人なりの仕事のやり方を見つけて最適化することで成果を出していくもの。
新人教育において、先輩社員や教育担当者がやるべきことは、その過程に、寄り添いつつ、困ったことがあればサポートし、新人が自分なりのやり方を見つけていく手助けをすることです。
このことをしっかりと理解すれば、「新人いびり」や「新人いじめ」なんて、なんの生産性もないことをおこなう社員は減っていくはず。
新人いびりの心理「新人をいじめる人」の問題と取扱方法【まとめ】
以上、職場における「新人いびりをする人」や、「新人をいじめる人」の問題について、整理しつつ、その取扱方法について考察してきました。
新人いびりや新人いじめのパターンとして、「ミスに対して、必要以上に厳しく指導する」、「新人の仕事のあら捜しをして、些細なことに怒る」といったものが典型的です。
この背景、心理としては、
・日頃のストレスのはけ口として、新人いびりをしている
・職場での自己の保身や、他者へのマウンティングや嫉妬から
といった悪意のあるものや、
・目の前の仕事への無駄に強い責任感
・歪んだ正義感とおせっかい
・無垢な新人への自身の価値観の押しつけ
といった、すこし歪んだ責任感やプレッシャーから、必ずしも意図的に「新人いびり」をしているわけではないケースもあります。
とはいえ、いずれのケースも、結果的に新人が成長しなかったり、「新人いびり」「新人いじめ」に耐えられず辞めてしまったりすると、組織にとって大きな損失となってしまうのです。
そのため、組織としては、
・「新人いびり」「新人いじめ」をする人を新人から遠ざける
・「新人いびり」「新人いじめ」をする人の職場で心理的安全性を確保する
・新人教育に関して無駄に大きなプレシャー、責任感を負わせない
・新人には「指導」や「お説教」ではなく「寄り添う」ことが重要と理解してもらう
といった上司あるいは同僚の働きかけを、「新人いびりをする人」「新人いじめをする人」に対して行うことが必要かつ効果的な対策となります。
それじゃあ今回はこれくらいにしておきます。
新人いびりがある会社なんかろくなもんじゃねえ!転職するのもあり?:
おすすめ!
初めての方、転職初心者向けの第一歩はリクナビNEXTの「無料会員登録」一択です
・転職活動の効率を上げる会員限定機能が無料で利用できます!
新着求人情報をメールで受信
「気になるリスト」で企業を保存
一度レジュメを書いて保存すれば転用可能
自分の強みを把握できる「グッドポイント診断」
・スカウト登録(無料)で転職の選択肢が広がる!
→匿名で職務履歴や条件を登録すれば、企業やエージェントから直接オファーが届く
【メリット】自分のスキルや経験を活かした企業を効率よく探せる、忙しくても転職活動ができる
そんな方には、リクナビNEXTがおすすめ:無料会員登録はこちらのリンクです↓
・転職活動の効率を上げる会員限定機能が無料で利用できます!
新着求人情報をメールで受信
「気になるリスト」で企業を保存
一度レジュメを書いて保存すれば転用可能
自分の強みを把握できる「グッドポイント診断」
・スカウト登録(無料)で転職の選択肢が広がる!
→匿名で職務履歴や条件を登録すれば、企業やエージェントから直接オファーが届く
【メリット】自分のスキルや経験を活かした企業を効率よく探せる、忙しくても転職活動ができる
そんな方には、リクナビNEXTがおすすめ:無料会員登録はこちらのリンクです↓
では。
あわせて読みたい
「上司と話すのが怖い」「上司と話すと涙が出る」は危険信号?!:原因と対処法7つ
上司のお気に入り部下は嫌われる?!職場で「上司のお気に入りと言われる」は危険!上司としても態度に注意するべき理由
その他の投稿記事一覧はこちら
よろしければtwitterフォローお願います
Follow @CU4rLznEer9Ku5G
注目の記事
その他の投稿記事一覧はこちら
よろしければtwitterフォローお願います
Follow @CU4rLznEer9Ku5G